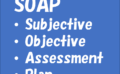最近、「ネイバーフッド(近隣住区)」が見なおされているという話を時々聞きます。
よく紹介されているのは、パリのアンヌ・イダルゴ市長の「自転車で15分の街」という都市計画の提案。2020年の統一地方選に向けて、2024年までに誰もが車ナシでも15分で仕事、学校、買い物、公園、そしてあらゆる街の機能にアクセスできる都市を目指すと宣言し、見事に再選を果たしたのです。自転車で15分というと3~5kmぐらいは走れるので、実は結構な広がりがあるかもしれないのですが、それでもコンパクトな地域のイメージが伝わってきます。
折しも、コロナ禍で3密回避が注力されるなか。都心への通勤制限、テレワークの普及浸透とあいまって、地域コミュニティのあり方が見直されているタイミングで、「自転車で15分の街」は、わかりやすいまちの将来像モデルとして注目を集めました。
+++
一方、徒歩圏に必要な機能を整備するという「ネイバーフッド(近隣住区)」の考え方そのものは、都市計画の古典的な考え方のひとつ。1920年代に米国の社会学者クラレンス・A・ペリーが体系化し、小学校区を構成するニュータウン計画の基本的な考え方となりました。今は絶版となってしまったようですが、私の大学時代は必読書のひとつで、小学校区のダイヤグラムは今でも鮮明に覚えています。また、同書には、様々な機能が成立する支持人口の考え方が示されており、計画的な機能立地を考えるうえで大いに参考になりました。
ただ、ニュータウンで展開された近隣住区論に対しては、少なくとも2つの批判があったと思います。
ひとつは近隣住区を単位として、空間を構成するニュータウンが、人間の社会的つながりとは一致しないという批判。クリストファー・アレキサンダーが「都市はツリーではない(A city is not a tree)」という論文で痛烈に批判しました。空間的に分断された住区を超えた付き合いもあるだろうという批判は説得力があり、柔軟な交流を可能とするグリッド型の道路パタンの導入等、ニュータウンの空間構成に対する考え方が変わるきっかけになったと記憶しています。
もうひとつは、ニュータウンの密度の低さや単調さに対するジェーン・ジェイコブスによる批判です。ジェーン・ジェイコブスは、やはり都市計画論の古典のひとつ「アメリカ大都市の死と生」で、郊外部の住区はともかくとしても、人々は多様で高密度な都市空間を求めているという主張を強く主張しました。ニュータウンにおける無味乾燥なタウンセンターではなく、多様性を享受できるまちなかの空間にこそ価値があるということです。
こうした2つの批判にさらされる中で、理論としての重要性はともかくとして、近隣住区論自体に対する注目度は下がってしまったままだったように思います。それだけに、なぜ再び注目されているのかが気になってしまいました。
+++
考えて思い至ったのは、「ネイバーフッド(近隣住区)」の注目ポイントが、かつてのニュータウン計画を議論されていたころとは違ってきているのではないかということ。要は重視する価値の変遷があるということです。
都市計画の単位として近隣住区が注目されていたころは、ニュータウンの空間、機能を構成する計画単位としての役割、すなわち経済合理性が重視されていたようですが、今日、重視されているのは、社会の持続可能性のように思います。これが具体的には、パリの都市計画でいえば大気汚染や気候変動への対策であり、我が国のウォーカブルシティでいえば、人々の居心地の良さだったりするのではないかと思います。
SDGsで示されている今日的な価値観からみると、忘れ去られた取組に価値が潜んでいることが他にもありそうです。できれば、こうした埋もれた価値の発掘作業に取り組んでみたいと思います。

出所) ECF: European Cyclists’ Federation https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-towards-15-minute-cities